こんにちは、Himaです。
俳句の世界では、「花火」は夏の季語ですね。
全国各地で今、花火大会が行われていますね。
浴衣着て花火を観る……最高にロマンティックですね。
特に8月はお盆の時期です。私たちのご先祖様の霊をお迎えし、
そして送りだす、弔いの意味もあります。
その中でも、線香花火は江戸時代に作られた日本おもちゃ花火の代表的な存在で
多くの人々に長い間、親しまれてきました。
Himaも線香花火が大好きで、火の玉がポトっと落ちないように、
花火を持っている腕を動かないよう座ってジーっと、
眺めていました。
そんな線香花火について、
NHKさんが『探検ファクトリー』で「江戸時代の製法を守る 線香花火工場を探検」
を、特集していました。
面白そうでしたので、ご一緒に観ていきたいと思います。
線香花火は西日本と東日本で何が違うの?
線香花火に関西と関東の違いが有るって知っていましたか?
私は知りませんでしたが、記憶を辿ると両方使ったことがありました。
先ずは関東の線香花火は和紙に包まれた「長手牡丹」といい、今現在も主流で
スタンダードな線香花火です。
東日本では紙漉きが盛んだったこともあり、紙撚りの線香花火となったようです。
関西を中心として西日本で親しまれてきたのが、米ワラの芯で作られた線香花火
「スボ手牡丹」です。
こちらは、江戸時代に作られた元祖線香花火です。
このように、地域によって親しまれてきた線香花火は違うことが分かりました。
あなたの思い出の線香花火はどっちでしょうか?
Himaは、どちらも遊んだことがあります。
でも、ワラ芯のほうがパチパチと火花が飛ぶ感じを早めに感じる気がします。
(あくまで個人の感想です)
現在は、国産の線香花火を制作しているのは、3社のみになっていて、
和紙の線香花火が主流で1年中作られているとのことです。
ワラの線香花火に関しては国内では1社のみとなっています。
線香花火の名前の由来は遊び方にあった!
現在主流の線香花火は、手持ちで下向きに持って遊びます。
元祖線香花火のワラ芯のものは、手持ちで下向きに持って、同様の遊び方
でいいのですが、線香のように”上向き”にしても遊べます。
昔は、まさに線香っぽく、高炉に立てて遊んでいたんです。
これが「線香花火」と言われる由来です。
大人が遊ぶなら静かに高炉に刺して、線香花火を愛でるのも
ちょっぴりおしゃれで、ロマンティックな夜になりそうですね。
線香花火を長持ちさせるコツを伝授します!
線香花火の火薬の量はわずかの0.08グラムです。
この少しの量で火花の出方が変わるデリケートな繊細さんなのです。
線香花火の持ち方一つでも長持ち度合いは変わってきます。
①線香花火が長持ちする持ち方
私もふくめて皆さん、花火を真下に垂らして持っていますよね?
実は線香花火の持ち方は、斜め45度の角度で持つと火玉が和紙のこよりに
乗りやすくなり、中の火薬が安定しやすいのだそう。
②線香花火を開封した時に長持ちさせる工夫は?
線香花火は、商品の流通過程で少しこよりが、ほどけてしまっています。
先ずは、線香花火に火を点ける前に、火薬が詰まっている先端部分のくびれを、
指で軽くひねって火薬をまとめておきます。
これは、こよりを再度ねじることで強度が増し、火玉が安定するからです。
③線香花火の点火時の長持ちの工夫とは
線香花火に火を点けるとき、炎の先端でそうっと、火を点けると
ゆっくりと線香花火はスタートします。
すると火玉がボトッと落ちにくくなります。
#線香花火 関西関東
#線香花火長持ちさせる
#花火 技 長持ち

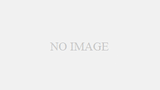

コメント